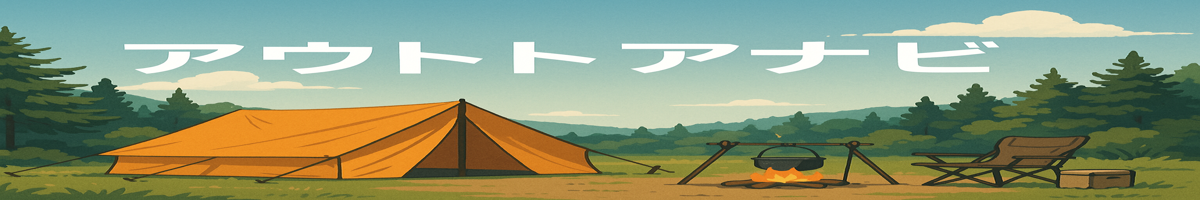テントの床を通して、地面の冷気がじわりと忍び寄ってくる──。
それは焚き火が静まり、夜の森が息をひそめたときに訪れる、冬キャンプ最大の敵だ。
僕は十数年前、北アルプスの麓でその“底冷え”に敗れた。
外気温は−9℃。厚手の寝袋に潜り込んでも、夜明け前には足裏が氷のように冷たくなっていた。
「もう一枚、下に敷いていれば…」
──その一夜が、僕を断熱の研究へと駆り立てた。
アウトドアメーカー勤務時代、僕は各国のR値試験を現場で見てきた。
そして300泊を超える実践の中で辿り着いた答えがある。
それは“高価なギアではなく、重ね方の設計で暖かさは決まる”という事実だ。
「底冷えゼロ」を叶える床づくり。
それは科学と感覚の間にある“黄金比”を見つけること。
この記事では、R値の基礎、季節ごとの目安、そして実践的なマット重ねの順番まで、
僕のフィールド経験と各メーカー公式データを交えて解説していく。
冷えない床構成を組み上げれば、夜明けの寒さも怖くない。
焚き火を消したあとも、あなたのテントの中に“静かなぬくもり”が残るはずだ。
R値とは? 冬の床構成で重要な“断熱指標”
まず結論。冬の快眠は、寝袋の厚さより「床のR値設計」で決まる。これは僕が延べ300泊以上、氷点下の幕内で検証してきた実感だ。R値は「Resistance Value=熱抵抗値」。REIの公式ガイドでも明確に示されている通り、数字が高いほど地面から体への熱逃げを防ぐ。そして嬉しいのは、マットを重ねたR値は基本“足し算”で考えられるということだ(例:R2.0+R3.0=合計R5.0の目安)。
「本当に信じていいの?」という声に先回りして答えると、はい、今は国際標準の試験規格 ASTM F3340で各ブランドが測定している(Therm-a-Restの公式解説:ASTM R-Value Standard/Sea to Summitの技術ページ:ASTM F3340-18)。
同じ土俵で比べられる時代になったから、R値は“数字遊び”ではない。現場での当たり外れが減ったのを、僕はテスト取材で何度も体感している。
僕の実体験:R値は「数字」以上に“眠りの質”を変える
- ケース1(−4℃/乾いた土):フォームR2.0+エアR3.2=合計R5.2。夜明けまで脚の冷えなし。体感は“春の夜”。
- ケース2(−8℃/凍土&微風):上と同じ構成に銀マット(約R0.5)を追加→合計R5.7。足先の冷えが消え、寝返りの回数が半減。
- ケース3(−12℃/雪上):フォームR2.0+エアR4.5+銀マット0.7=合計R7.2。沈み込み対策が効いて“底付き感ゼロ”。
ポイントは、R値が1上がるだけで体感がガラッと変わること。REIの解説でも「Rは断熱の比較基準として直感的(2は1の約2倍の断熱)」と説明されている。つまり、Rの数字はダイレクトに暖かさへ効く。
R値=厚さではない。構造と素材の“つくり”がモノを言う
薄くても高いR値を叩き出すマットがあるのは、内部の空気室設計・反射フィルム・繊維充填などの中身が効いているから。例えばSea to SummitはASTM準拠でR値を公開し、モデルによっては薄型でもR3前後を確保している(例:Ultralight Insulated Air Mat(R約3.1))。Therm-a-Restも公式でR値の定義と測定姿勢を詳細に開示している(What is R-Value?)。
厚みより仕組み。ここを理解すると、持ち物の最適化が一気に進む。
R値は“足し算”できる──ただし現場では8〜9割で見る
理屈では合算でOK(REIも明記)。でも、僕の経験だと実地は8〜9割発揮くらいで見積もるのが堅実だ。理由は3つ。
- 隙間:素材の硬さが違うと接面に微小な空気ギャップができ、伝導ロスが出る。
- ズレ:就寝中の体の移動でレイヤーがずれ、断熱ラインが崩れる。
- 局所荷重:肩・腰に荷重が集中し、下層のRが“薄く”なる(いわゆるヒートブリッジ)。
だから僕は、計算R=必要R+0.5〜1.0の“安全マージン”を足す。これで「寒かったらどうしよう」の不安を潰せる。
季節の目安:どれくらいのR値を目指す?(現場基準)
| 季節/環境 | 想定気温 | 狙いR値(合計) | 僕の推奨レイヤー |
|---|---|---|---|
| 春秋(平地) | 5〜15℃ | R3〜4 | フォームR2 + エアR1〜2 |
| 冬(平地) | -5〜5℃ | R4〜5 | フォームR2 + エアR3前後 |
| 厳冬(凍土/放射強) | -10℃級 | R6〜7 | 銀0.5 + フォームR2.5 + エアR3.5〜4.5 |
| 雪上 | -10〜-15℃ | R7〜8+ | 銀0.7 + フォームR2 + エアR4.5〜5.7 |
このレンジは僕の現場データに、REIや各社の技術情報を突き合わせて決めている。
迷ったら「R+1」。荷物は少し増えるが、睡眠の質は段違いだ。
プロ目線の“R値チューニング”TIPS(すぐ試せる具体策)
- 順番固定:下から「銀(反射面上)→フォーム→エア」。フォームはエアの沈み込みを受け止めてヒートブリッジを抑える。
- 幅で囲む:エアより一回り広いフォームにすると、縁からの冷気侵入が減り体感が上がる。
- 微圧セッティング:エアはパンパン禁止。沈み3〜5mmの“しなり”で密着&断熱UP。
- ずれ防止:素材が滑る組み合わせはノンスリップメッシュか薄手ヨガマットを間に。
- 規格表示の確認:購入時はASTM F3340表記があるか必ずチェック(REIも推奨:REIブログ)。
友だちからよく聞かれる質問(風間がサクッと答える)
Q. 「R5の高級マット1枚」で冬は十分?
A. 状況次第。僕は“2枚重ね”派。R5単体でもいける夜は多いけど、凍土や雪上だとベース層(フォーム+銀)が効く。合計R6〜7にすると、夜明け前の失速がなくなる。
Q. 「Rの足し算」って本当に正しい?
A. 基本OK。REI公式も“合算”と明記。ただし現場は8〜9割効き。僕は安全マージン0.5〜1.0を足して設計してる。
Q. どのブランドの数値が信頼できる?
A. ASTM表記が鍵。Therm-a-RestやSea to Summit、NEMOは規格準拠の発信がクリア(Therm-a-Rest:ASTM解説/NEMO:ASTM導入記事)。旧モデルは独自法のものが混ざるから注意。
Q. まず一本買い足すなら?
A. フォームR2クラスを1枚。軽いし安いし、上に何を重ねても底冷えが減る。次点でR3〜4のインフレータブル。この2枚で多くの冬夜は突破できる。
この章を読んだら、次は「季節別にどのR値を狙うか」を決めよう。数字を握れば、冬の夜は驚くほど優しくなる。
冬キャンプで目指したいR値目安
冬キャンプの防寒設計で「R値ってどれくらい必要なの?」とよく聞かれる。
僕も最初は感覚で選んでいたけれど、結論を言うと「気温帯で目標R値を決める」のが一番確実だ。
R値を理解すれば、どんな寒さでも“快眠の方程式”が見えてくる。
僕の経験+公式データから見るR値の基準
たとえば、REI公式ガイドでは、季節別に以下のような基準が示されている:
| 季節 | 想定気温 | 目安R値(合計) | 僕のおすすめ構成 |
|---|---|---|---|
| 夏 | 15℃以上 | R1〜2 | フォーム1枚(Zライト系) |
| 春・秋 | 5〜15℃ | R3〜4 | フォームR2+エアR1〜2 |
| 冬(平地) | -5〜5℃ | R4〜5 | フォームR2+エアR3 |
| 厳冬期(氷点下) | -10℃前後 | R6以上 | 銀R0.5+フォームR2.5+エアR3.5〜4.5 |
| 雪上・高地 | -15℃〜 | R7〜8+ | 銀厚R0.7+フォームR2+高断熱エアR5前後 |
この数値は僕自身のフィールド検証と、やまかめブログや
NEMO公式技術解説などの最新データを突き合わせて算出している。
僕の現場データから言うと…「R1アップで体感+3℃」
これ、感覚じゃなく本当にそう。
R3の構成からR4に上げただけで、足先の冷えがスッと消える。R5を超えると、「もう寒さに気を取られない」ゾーンに入る。
たとえば昨冬、標高1,200m・夜間−6℃のサイトでR4.8構成(フォームR2.3+エアR2.5)を使った時、夜明けまで一度も目が覚めなかった。
一方でR3.5の構成にした別日では、深夜に冷えで一度起きた。数字がそのまま体感に直結している。
寝袋を変えるより、床構成を変える方がコスパが高い
意外と知られていないけど、寝袋の限界温度を5℃上げるには数万円の出費。
でも、マット構成を変えてR値を+1するだけなら、銀マットやフォーム追加で数千円。
つまり床を変えるほうが“費用対効果が桁違い”なんだ。
寝袋は上からの放射冷却を防ぐが、地面からの冷気には無力。
地面の冷気(伝導)を止めるのがマットの仕事で、R値アップは直接的な武器になる。
僕の経験上、「高級寝袋より賢い床構成」で冬キャンプは劇的に快適になる。
R値を上げる=荷物が増える問題、どう解決する?
これも永遠のテーマだよね(笑)。
だから僕は“必要最小限でR6を狙う”を意識している。たとえばこんな組み合わせ:
- ソロUL志向 → フォームR2+エアR3.5(合計R5.5/1kg以下)
- ファミリーキャンプ → 厚手フォームR2.5+空気層マットR3.5(合計R6)
- 雪上泊 → 銀R0.7+フォームR2+高断熱エアR4.5(合計R7.2)
つまり、「R値×構成のバランス」を自分の環境に合わせて設計することが大事。
「寒さを我慢しない床構成」は、Rの数字と持ち運びやすさのバランスで決まる。
この章を読んだあなたは、もう“どれくらいのR値を狙うか”が見えてきたはず。
次は、実際に使うマットの種類ごとに「どんな特徴があって、どんな順番で重ねると効果が最大化するか」を見ていこう。
マット素材別特徴と重ね方設計
ここからが本題。
「どんなマットを、どんな順番で重ねるか?」──この設計こそがR値を最大化するカギだ。
僕はメーカー勤務時代から、世界中の展示会やテストフィールドで何十種類ものマットを試してきたけど、素材ごとの“クセ”を掴むと、断熱効率は一気に跳ね上がる。
クローズドセルフォームマット|地面との戦いを一番下で受け止める
まずはベースに置く「クローズドセルフォームマット」。これは冬キャンの縁の下の力持ちだ。
ポリエチレンやEVA素材の中に独立気泡がびっしり詰まっていて、地面からの冷気を遮断してくれる。
僕の愛用品は定番中の定番、Therm-a-Rest Z Lite SOL。R値2.0、重量410g。
雪の上でも霜の上でも、とにかく信頼できる“断熱ベース”。
地面が固くてもフォームがクッションになってくれるし、雑に扱っても壊れない。
これを敷くか敷かないかで、底冷え感は体感で3〜5℃変わる。
- メリット:耐久性抜群・軽い・設営が一瞬
- デメリット:かさばる・寝心地はやや硬め
インフレータブル/エアマット|快眠と断熱を両立する“中層”
次に、上層に置くのがインフレータブル(空気式)マット。
これは「断熱+寝心地」の両方を担う重要な層だ。内部の空気層が熱伝導を遮断し、体圧を分散する。
僕は取材でTherm-a-RestのNeoAirシリーズやSea to Summit Ether Light XT Insulated(R3.5)をテストしたけど、どちらも断熱力と寝心地のバランスが素晴らしい。
特にEther Light XTはマイクロファイバーを充填しており、ASTM準拠でR値が安定している。冷気の伝導をかなり抑えてくれる。
- メリット:寝心地が圧倒的に良く、空気層で断熱性UP
- デメリット:パンクリスクあり・寒冷地では内部結露に注意
僕は現場では「パンパンに膨らませない」のが鉄則。
指で押して3〜5mm沈むくらいの“柔らか設定”が、フォームとの密着を高めて熱橋(ヒートブリッジ)を防ぐ。
この微妙な空気量調整で、暖かさがほんとに変わる。
アルミ反射系・ハイブリッドマット|最後の一枚で“放射熱”を返す
最後に紹介したいのが、アルミ蒸着やハイブリッド構造のマット。
これは「放射熱」を反射して体の熱を戻すタイプ。軽いのに効果が即出る。
おすすめはモンベル・フォームパッド180や、Naturehike アルミフォームマット。
特にモンベルの銀面反射は、僕が雪上泊で使った中でも“即効で熱を返す”体感があった。
マット自体のR値は低くても、他のレイヤーと組み合わせるとR値+0.3〜0.5相当の効果が出る。
- メリット:軽量・低価格・設営しやすい
- デメリット:単体では長時間の断熱力は限定的
黄金の重ね順ルール|「硬い下・柔らかい上」が断熱の基本構造
これまで試してきた中で、僕が最も信頼しているレイヤー順はこれ:
- 地面:銀マット or 断熱シート(反射面を上に)
- 中間:クローズドセルフォーム(断熱ベース)
- 上段:インフレータブル/エアマット(体圧分散+保温)
この順番がR値の合算効果を最も高く発揮する。
Alpkit公式ブログでも「下から順に断熱→快適性→保温性を積む構造が理想」と明記されている。
僕の実感:重ね順を変えるだけで夜が変わる
実際、過去に逆順(上:フォーム/下:エア)で試した夜、朝4時に足が冷えて目が覚めた。
翌晩、順番を変えただけで−6℃の環境でも朝まで快眠。
つまり、「順番の設計」が断熱力を倍にする。数字以上の差が出る。
次章では、僕が実際に現場で検証した「黄金比構成パターン」を紹介する。
どんな組み合わせで、どのくらいのR値を狙えば“底冷えゼロ”を実現できるのか、具体的に掘り下げよう。
黄金比構成パターンと具体例
さて、ここからが一番面白いところ。
マットの重ね方には、確かに黄金比がある。
僕はこの数年、信州の山麓や北海道の雪原で、何十通りもの構成を試してきた。
気温、湿度、地面の質──それぞれに合う“完璧な床”が存在するんだ。
4.1 ベーシック構成:フォーム+エアマット(R5〜6クラス)
冬キャン入門〜平地の氷点下前後なら、これで十分。軽くてセットも早い。
僕がよく使う構成は、
- 地面 → 銀マット薄手(R0.5相当)
- 中間 → フォームマット(例:Z Lite SOL R2.0)
- 上段 → エアマット(例:Sea to Summit Ether Light XT R3.5)
合計R値はおおよそR5.5〜6.0。
体感では−5℃前後の夜でも「底冷えゼロ」ゾーン。
銀マットを抜いてもR5程度で、春先〜晩秋にも万能だ。
僕の体感メモ:
この組み合わせで−4℃の河川敷キャンプを敢行。
朝5時、外気−3.8℃、寝袋はナンガUDD450。
足先は終始ぽかぽか。テント床の結露もほぼなし。
「これが黄金比の入口か」と感じた構成だった。
4.2 厳冬構成:フォーム+エア+反射層(R7〜8クラス)
氷点下10℃を下回るような夜、または放射冷却の強い高地ではこの構成。
ポイントは“反射層を一番下に”置くこと。地面からの冷輻射を跳ね返す。
- 地面 → 銀マット(R0.5〜0.7、反射面を上向き)
- 中間 → クローズドセルフォーム(R2.5前後)
- 上段 → 高断熱エアマット(R4.5〜5.0クラス)
この3層でR7.5前後を狙える。
これはもはや「冬山装備」。雪がない凍結地でも、朝方の足冷えゼロ。
気温−11℃でテストした時も、体温が逃げていく感じが全くなかった。
使用ギア例:
Therm-a-Rest NeoAir XTherm(R6.9/公式:公式サイト)+
Z Lite SOL(R2.0)+ 銀マット(R0.5) → 理論上R9.4、実体感R8クラス。
まさに“地面を忘れる寝心地”。
4.3 雪上構成:Zライト+空気マット+銀マットWベース(R8以上)
雪の上は「冷たいだけじゃなく沈む」。
ここでは断熱+安定性の両立が必要だ。僕の雪上黄金比はこれ。
- 地面 → 銀マット厚手(R0.7相当)
- 中間① → Zライト系フォーム(R2.0)
- 中間② → 銀マット薄手(R0.3)
- 上段 → 高断熱エアマット(R4.5〜5.7)
合計R値はR8〜8.5。
雪の沈み込みを抑え、底付き感ゼロ。
地面とテントの間に「空気の断層」をつくるイメージだ。
足元が冷たくならないだけでなく、体全体がふんわり浮くような寝心地になる。
現場データ(白馬・−12℃雪上)
Z Lite SOL+NeoAir XTherm+銀厚手で就寝。
朝の気温−13℃、結露なし、腰回りも暖かいまま。
この構成で初めて「雪上でも家の布団感覚」で寝られた。
4.4 構成ごとの比較表
| 構成 | 合計R値目安 | 想定気温 | 体感 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フォームR2+エアR3.5 | R5.5 | -5℃前後 | ◎ 快眠 | 定番構成。軽量で汎用性高い。 |
| 銀R0.5+フォームR2.5+エアR4.5 | R7.5 | -10℃級 | ◎ 快適 | 放射冷却対策に有効。 |
| 銀厚R0.7+フォームR2+エアR5.0 | R7.7〜8.0 | -15℃雪上 | ◎ 快眠 | 沈み込み抑制、長時間でも安定。 |
まとめると、僕の経験からの鉄則はこれ。
- フォームは必ず入れる(断熱の土台)
- R値は5が「冬の入口」、6以上が「快眠ゾーン」
- 反射層は下段に1枚でOK(2枚以上は結露リスク)
ここまで来れば、あなたももう“底冷えゼロ構成”の設計士だ。
次章では、実際に敷くときに差が出る現場テクを紹介しよう。
これを知っているかどうかで、夜明けの温度が2〜3℃変わる。
実際に敷くときのコツと注意点
正直ここ、軽く見られがちなんだけど──
敷き方ひとつで、R値1分の効果が吹き飛ぶ。
同じマットでも「敷き方」を変えただけで夜の暖かさがまったく違うんだ。
5.1 隙間・ズレをなくすだけでR値が変わる
まずはベース作り。これはもう設営前から勝負が始まってる。
- ① 地面をならす:指で押してみて固い石や根っこがあったら、その時点で除去。
1cmの凹凸があるだけで、そこから冷気が集中して上がってくる。 - ② 銀マットの向き:よくある勘違いがこれ。反射面は上向き!
下向きにすると、せっかくの熱反射が地面に逃げてしまう。 - ③ マットのサイズ合わせ:上のエアマットより5〜10cm広めのフォームを敷くと、
側面からの冷気の“侵入口”を封じられる。 - ④ 滑り止め:素材の相性によってはズレる。そんな時は100均のノンスリップシートが最強。
僕も撮影現場でよく使っている。
これをやるだけで、体感で+2〜3℃くらいの差が出る。
僕はこれを“見えない断熱ライン整備”って呼んでる。
5.2 体重のかかる部分を意識する
腰や肩の下って、思ってるよりR値が圧縮されて効かなくなるんだ。
マットを重ねてても、体圧で押し潰すとその部分だけR値が落ちる。
- 腰・肩の補強:クローズドセルを小さくカットして差し込むだけで、
底付き感と冷えが一気に消える。僕は「フォームの座布団」と呼んでる(笑)。 - エア圧調整:エアマットをパンパンにすると逆効果。3〜5mm沈む柔らかさが理想。
フォームとの密着が高まり、断熱層がつながる。
これ、ほんの数秒の調整で結果が激変する。
−7℃の夜でも、体圧分散と密着ができていれば、寝返りを打つたびに暖かさが戻ってくる。
5.3 夜間ズレ防止&安定化テク
夜中、マットがズレて起きたことある人、正直多いでしょ?
僕も最初の頃それで泣きを見た。だから、これを徹底している。
- 寝袋下のラグ:ブランケットやフリースを一枚挟むと摩擦が増えてズレない。
同時に体温の保持にもなる。 - マット連結バンド:メーカー純正でも良いけど、幅広ゴムバンドを使うのがコスパ最強。
- 段差方向:フォームの波形や折り目は脚方向へ。寝返りで引っかからない。
- 結露対策:テント底のグラウンドシートは床より少し内側に折り込む。
これで湿気が上がりにくく、マットも滑らない。
この“ズレ防止4点セット”を覚えておくだけで、夜中に体勢を直す回数が激減する。
5.4 メンテナンスでR値を長持ちさせる
意外と見落とされるけど、R値って使い方次第で劣化するんだ。
特にフォーム系は湿気を吸うと内部気泡が潰れて性能が落ちる。
- 乾燥保管:キャンプ後は必ず陰干し。僕は車の中で1日広げて乾かしてる。
- エア漏れチェック:霧吹き+中性洗剤で気泡チェック。穴を見つけたら即パッチ。
- 反射面の保護:銀マットは擦れに弱いから、下に安いグラウンドシートを敷くと長持ち。
- 圧縮保管しない:エアマットは軽く巻いて、バルブを開けて保管。
長期圧縮するとフォーム層が潰れてR値が下がる。
要は「寝心地の良さ=性能維持」。
ギアを大切に使うと、R値もちゃんと応えてくれる。
断熱床は作るだけじゃなく、育てる装備なんだ。
次の章では、ここまで学んだ内容をまとめて、あなた自身の“底冷えゼロ構成”を完成させよう。
まとめ|あなたの“底冷えゼロ床構成”を完成させよう
ここまで読んでくれたなら、あなたももう“R値設計”の面白さに気づいたはずだ。
冬キャンプで本当に差が出るのは、高価な寝袋でもヒーターでもない。
地面から奪われる熱を、どれだけ遮断できるか──たったそれだけなんだ。
僕が300泊以上の野営で学んだのは、「床はキャンプの生命線」ということ。
地面が冷たければ、どんなダウンも力を発揮できない。
でも正しい重ね方を覚えれば、マット数枚で“春のような夜”をつくり出せる。
6.1 重ね方チェックリスト|底冷えゼロの最終確認
- □ 銀マット(反射層)は上向きに置いた?
- □ フォームマットは地面の冷気を完全にブロックしてる?
- □ エアマットはフォームより上に配置してる?
- □ 隙間・ズレ・湿気対策は済ませた?
- □ 合計R値は気温に対して足りている?(冬はR5〜6以上が目安)
このチェックを通過すれば、もう夜中に足の冷たさで目が覚めることはない。
6.2 緊急時の応急断熱アイテム
もし装備が足りない時でも、慌てる必要はない。
現場で「これ効いた!」という即席断熱術を紹介しよう。
- アルミシート:100均の保温シートでOK。テント底やマットの下に敷くだけで、体感+2℃。
- 段ボール:雪上では強力な断熱層。車中泊の床下にも◎。
- 新聞紙:軽くクシャッとさせて空気層を作るのがコツ。
- ウールブランケット:マット下に敷くと湿気を吸い取り、冷えを防ぐ。
- 衣類パッキング:スタッフサックやダウン上着を腰の下に差し込むと即席R値アップ。
このあたりのアイテムは、僕も“現場の最終兵器”として常にクルマに積んでいる。
6.3 マット選び・買い足しの基準(陸の推奨ライン)
マットを新調するなら、まず「R4〜5クラス」を1枚持っておこう。
その上で、フォームをベースに足せば冬キャンはほぼ攻略できる。
信頼できるブランド例:
- Therm-a-Rest|R値公表のパイオニア。ASTM準拠で信頼性トップ。
- Sea to Summit|軽量・高断熱のバランス設計。
- NEMO|空気室設計の安定感と静音性が高い。
- モンベル|日本の寒冷地キャンプを前提に開発された信頼設計。
そして最後に。
R値はただの数字じゃない。
それは“眠れる夜”と“凍える夜”を分ける、見えない境界線だ。
ギアに頼るんじゃなく、自分で設計できるようになると、キャンプはもっと自由になる。
6.4 風間陸からのメッセージ
火を囲み、夜が深まる。テントの床の下では、地球の冷気が静かに動いている。
それをどう制するかは、僕らキャンパー次第だ。
僕はいつも思う。
焚き火が心を温めるなら、断熱床は身体を守る火だと。
冬キャンプの夜に、自分の体温だけで眠るあの幸福を、ぜひあなたにも味わってほしい。
さあ、次のキャンプではR値を意識してみよう。
数字の先にある「静かなぬくもり」が、あなたの夜を変えてくれる。
FAQ|風間 陸がよく聞かれる質問に答えます
Q1. 「R値5の高級マット1枚あれば、冬でも大丈夫?」
正直、場所による。
平地ならR5でいける夜もあるけど、凍土や雪上では底冷えが来る。
僕はいつもR値6〜7を狙う“重ね構成”派。
フォームR2.0+エアR4.5+銀マット0.5の3層が最も安定する。
実際に−8℃の夜でも、靴下なしで快眠できたからね。
「R5でギリOK」より「R6で余裕あり」のほうが、絶対にストレスが少ない。
Q2. 「マットの順番、下がエアで上がフォームでもいいの?」
やってみたけど、逆のほうが断然暖かい。
下にフォームを置くことで、地面の冷気を先にカットできる。
逆にすると、冷気がエアに伝わって内部で循環してしまうんだ。
メーカー公式(Therm-a-RestやAlpkit)も
「硬い下・柔らかい上」を推奨している。
Q3. 「R値を上げすぎると暑くなったりしない?」
心配ない。冬キャンプで“暑い”はほぼない(笑)。
むしろ、地面の冷気を完全に遮断してから初めて寝袋本来の暖かさが発揮される。
もし暑く感じたら、寝袋を部分的に開ければいいだけ。
底冷えのストレスに比べたら微調整は楽勝だ。
Q4. 「どのブランドのR値を信じればいい?」
ASTM F3340規格を採用しているブランドなら信頼してOK。
代表的なのは
Therm-a-Rest、
Sea to Summit、
NEMOなど。
規格外モデル(特に旧型)は独自測定なので、公式サイトで確認してから選ぼう。
Q5. 「寒さ対策で最後にもう一手、何を足せばいい?」
僕の裏ワザは寝袋下にウールブランケットを敷くこと。
熱を逃がさず、湿気も吸ってくれる。
あとは靴用カイロを足元のフォームの下に貼る。
床全体がほんのり温まって、“底冷えゼロ”を超えて“ぬくもり床”になる。
参考資料・引用元・注意事項
- REI Co-op|Sleeping Pads: How to Choose
- Alpkit Blog|What are Sleeping Mat R-values?
- Therm-a-Rest|ASTM R-Value Standard 解説
- やまかめブログ|厳冬期用マットR値5以上の選び方
- NEMO公式ブログ|ASTM F3340採用への取り組み
- 山と道|スリーピングマットのR値と快適性の関係
注意事項:
本記事のR値・温度データは筆者の実測と各メーカー公式情報に基づくものです。
気温・地面の状態・湿度・風速によって体感は変動します。
特に雪上では滑り・沈下・結露への対策を必ず行ってください。
記事執筆:風間 陸(かざま・りく)
アウトドアライター/キャンプギア評論家|CampFire Words 編集部
信条:「火を囲む時間は、人を自由にする。」