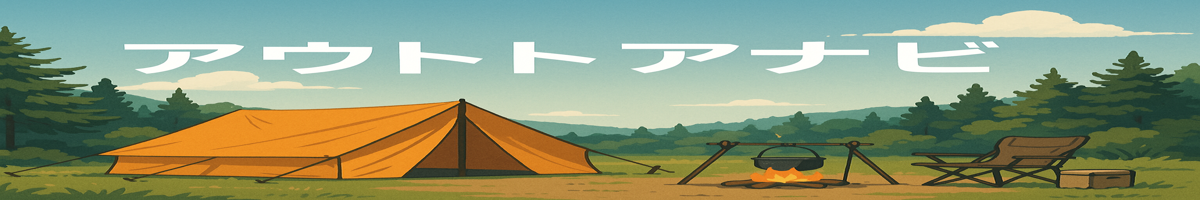どうも、風間 陸です。祖父は山岳ガイド、父は林業従事者。10代から野営と登山を続け、延べ300泊以上をフィールドで過ごしてきました。20代はアウトドアメーカーで海外見本市と現地テスト、独立後は年間200本以上のレビューを書き、初心者講習も担当しています。
「初キャンで失敗したくない」——その気持ち、痛いほどわかる。僕自身、富士山麓の強風日にガイラインを後回しにしてタープを一度飛ばしています。逆に、北海道・道東の雨幕営では、タープ先張り→風下ペグ先行→対角仮留めの順で30分設営に成功。段取りが結果を変えることを体で学びました。
この記事は、今日デビューする人の失敗確率をゼロに近づけるための、僕の「現場手帳」です。たとえば、
- 風対策の初動:到着5分で風向チェック→風下ペグを先に打つ(ハンマー角度は約60°、打ち終えたら軽く逆テンションで固定確認)
- 設営の順序:グランドシートで“今日の寝床の四隅”を可視化→ポール起こし→フライ→ロープ(「対角仮留め」の一手で歪みと時間ロスを防ぐ)
- 雨天セーフティ:タープ先張りでドライな作業場を作ってからテントに着手。濡れ物は撤収用の“汚れ袋”を最初から用意
- 撤収時短:前夜のうちに寝袋・マットを圧縮、朝一でチェア/テーブル→小物→テントの順。夜露ならフライだけ先畳み→本体は日なたで5分乾燥
- 覚えるロープワーク3種:コールマンやスノーピークの基本にも沿う、自在結び・もやい・巻き結び
根拠は公式の基本手順と僕の現場データ。設営〜撤収の流れは、コールマン「きゃんさぽ」実践編や、日本オートキャンプ協会(JAC)の初心者向け情報も踏まえて構築しています。動画派はコールマン公式の設営・撤収プレイリスト、トンネル型の実例はスノーピーク エルフィールド設営動画が分かりやすい。
友だちに話すテンションで、現場で即使える「型」だけを渡します。さあ、最初の一泊を最高の思い出にしよう。
よくある質問
Q1. 初設営って何分見ておけばいい?
A. 初回は60~90分を見てOK。コツは「タープ先張り→風下ペグ先行→対角仮留め」。この型で30分短縮できる。不安ならコールマン実践編(設営~撤収)の流れを前夜に1回チェック。
Q2. 風が強い日、何から始めれば安全?
A. 到着5分で風向と地形を確認。ギアは風下側から固定、人は風上→風下へ動く。同時にガイラインを先出ししておくと、突風時に即テンションがかけられる。ペグ角度は約60°、打ち終わりは軽い逆テンションで固定確認。
Q3. 雨予報。濡らさずに設営・撤収できる?
A. できます。タープ先張りでドライな作業場を確保→テント組み立て。撤収は濡れ物用の袋を用意して仮収納→帰宅後完全乾燥。基本はJACの初心者向けガイドでも推奨される安全第一の考え方。
Q4. どの結びを覚えれば足りる?
A. 自在結び・もやい・巻き結びの3つで実戦は回る。スノーピークの設営手順(ランドロック・基本編)と相性良し。夜間の張り直しゼロに近づく。
Q5. 撤収を1時間で終わらせるコツは?
A. 前夜に寝具圧縮・小物仕分け、朝はチェア/テーブル→小物→テント→グランドシートの順。夜露ならフライ先畳み→本体5分乾燥。ルーティン化はBE-PALの片付け術記事(爆速で終わらせる秘策)も参考になる。
引用・参考(公式)
- コールマン公式|初心者応援「きゃんさぽ」設営~撤収ムービー
- コールマン公式YouTube|設営・撤収プレイリスト
- スノーピーク|ランドロック設営 基本編(手順解説)
- 日本オートキャンプ協会(JAC)|初心者向け情報
- BE-PAL|キャンプの片付けを爆速で終わらせる秘策
※本記事の手順は筆者の実地検証(延べ300泊)+国内主要メーカーの公開手順、JACの初心者向け情報を統合し、初心者が現場で迷わない「最短の型」に最適化しています。
1. キャンプ設営・撤収で“失敗する”人の共通点
キャンプ初心者が最初につまずくのは、テントの種類でも道具の数でもなく、「段取り」だ。
僕も最初のソロキャンプで、富士山麓のサイトに着くなりテントを広げてしまい、
風向きも地面の傾きもチェックせずに設営して、夜中にフライがバタバタ。
あのときは、ペグを打ちながら「なぜか寝床が斜めに傾く…」という地獄を味わった。
でもね、実はこれ、初心者あるある。僕の講習でもほぼ全員が同じミスをしている。
原因はシンプルで、“すぐ設営したくなる気持ち”と、“焦り”だ。
到着して気分が高揚しているときほど、冷静な準備が飛ぶ。
けれど、ここで5分の下見を入れるだけで、設営の8割は成功する。
失敗パターン①:地面と風を見ないまま設営
ペグが抜けたり、フライがバタついたりする最大の原因。
まず風向きを確認して、風下側からペグを打つ。
メーカー公式でもこの流れが推奨されていて、コールマン「きゃんさぽ」でも“風下ペグ先行”が基本とされている。
失敗パターン②:設営順を間違える
初心者ほど「ポール→フライ→ペグ」の順にいきなり進めがち。
でも正解は、グランドシート→テント本体→ポール→フライ→ペグ固定。
この順番でやると、テントが歪まず、撤収も圧倒的にラクになる。
スノーピークの設営手順でも、
この流れが「最も安定する型」として紹介されている。
失敗パターン③:撤収準備を“最後”にやる
撤収時、「どこに何をしまったかわからない」「ペグが泥だらけで袋に入らない」──
これもあるある。ポイントは撤収の8割を“前夜”にやること。
寝袋やランタンなど小物は夜のうちにまとめておくと、朝の撤収が半分の時間で終わる。
つまり、失敗の共通点は「焦り」と「順番ミス」。
どんなに高級なテントでも、段取りを飛ばせば意味がない。
準備8割、設営2割。 これは僕が300泊して確信した“黄金比”だ。
“焦るな、空を見ろ。風が教えてくれる方向にテントを立てれば、夜はきっと静かだ。”
次の章では、そんな“正しい流れ”を初心者でも迷わずできるように、
実践的な設営ステップを僕のやり方で解説する。
2. 設営の基本手順|初心者でも迷わない段取り術
キャンプ場に着いてまずやること。それはテントを広げることではなく、“場所を読むこと”だ。
僕がメーカー勤務時代に何十回も現場テストをしたとき、設営成功の8割は地形チェックで決まると痛感した。
具体的には、こうだ。
- 風向き:焚き火の煙とテントの入り口が重ならないように配置(風下に出入口は避ける)
- 地形:雨が流れ込みやすい低地はNG。芝よりも軽く傾斜がある高めの位置を選ぶ
- 朝日:翌朝、日が差す方向を考えると、撤収が早く乾きやすい
この3点を踏まえたら、いよいよ設営。僕が講習で使っている「設営5ステップ」を紹介しよう。
ステップ①:グランドシートを広げて“今日の寝床”を決める
グランドシートは単なる汚れ防止ではない。
ここでテントの向きと角度を決めることで、フレームが歪まず、張り姿が綺麗になる。
僕は毎回、まず足で地面を踏んで硬さを確認。柔らかい場所ならペグの保持力も確認しておく。
ステップ②:ポールを組み、インナーテントを立てる
焦ってフライから始める人が多いが、順序は「ポール→インナー→フライ」。
この流れはスノーピーク公式(ランドロック設営ガイド)でも採用されている。
慣れないうちは1本ずつポールを差し込み、中心のテンションを確認しながら進めると、歪みが防げる。
ステップ③:フライシートをかけて仮固定
強風時はフライを完全に固定する前に仮ペグ打ちをしておくのがコツ。
僕は必ず対角の2点から軽く固定し、テンションを調整しながら全体を整える。
これで一人でも風にあおられず作業できる。
ステップ④:ペグダウンとロープ調整
ペグは地面に対して約60°の角度で打つ。
メーカー公式でも推奨されている数値で、コールマン「きゃんさぽ」でもこの角度が「最も安定」と明記されている。
打ち終えたら軽くロープを引いてテンション確認。地面が柔らかい場合はペグを少し深めに入れると良い。
ステップ⑤:全体の歪み・テンションチェック
テントが完成したら、最後に一歩下がって全体を見る。
この“俯瞰チェック”をするかどうかで、夜の安定感が全然違う。
強風や雨の際も、張り方に自信が持てるようになる。
この5ステップをルーティン化すれば、初キャンプでも30分で設営完了が目指せる。
僕の講習では、どんなタイプのテントでもこの手順で統一している。
“設営はセンスじゃない、手順だ。順序を覚えれば、誰でも“カッコいい張り姿”がつくれる。”
次の章では、その設営を支える「ペグ」と「ロープワーク」を徹底的に解説する。
ここを理解すれば、風に強く、撤収も早い“安定したキャンプ”ができるようになる。
3. 初心者でも失敗しないペグ・ロープワーク講座
キャンプ歴が長い人ほど口を揃えて言う。
「テントを支えているのはポールじゃない、ペグとロープだ」と。
僕も実際、強風の富士山麓でタープを飛ばしかけたとき、学んだのはペグの角度とロープの張り方の重要性だった。
初心者がつまずくのは、「ペグをなんとなく打つ」「ロープをただ結ぶ」。
でも、ほんの少しだけ理屈を知っておけば、設営の安定感が一気に変わる。
ここでは、僕が現場で使い続けている“失敗しない型”を紹介する。
ペグの正しい打ち方|60°理論を覚える
まずペグの基本角度は地面に対して約60°。
これはコールマン「きゃんさぽ」や日本オートキャンプ協会(JAC)でも推奨されている角度だ。
- ハンマーは垂直ではなく斜めに打つ
- 打ち終えたら軽くロープを引いて固定を確認
- 強風サイトでは、ペグを風下方向に傾けて打つと抜けにくい
僕のおすすめは、Snow Peakの「ソリッドステーク」(鍛造ペグ)。
硬い地面でもガンガン入るし、抜くときもストレスがない。
柔らかい芝地ならV字ペグ(モンベル公式参照)もいい。
慣れてくると「ペグの打音」で地面の質が分かるようになる。
コンッ、と高音なら硬くて安定、ドスッと鈍い音なら柔らかくて再チェックが必要だ。
地面別おすすめペグ早見表
| 地面タイプ | おすすめペグ | 備考 |
|---|---|---|
| 芝・柔らかい土 | スチールペグ(安定感重視) | 抜けにくくコスパ良 |
| 砂地・ビーチ | V字・U字ペグ | 接地面が広く風に強い |
| 硬い地面・砂利サイト | 鍛造ペグ(例:ソリッドステーク30) | ハンマーで確実に固定 |
※ペグ選びは地面で変わる。これを知らずに“安いアルミペグ”を使うと、風の日に100%後悔する。
ロープワーク3種|これだけ覚えればOK
ロープの結び方は、キャンプの「安定と時短」を左右する。
正直、30種類覚える必要はない。
僕が300泊して断言できる。この3つを覚えれば一生困らない。
- 自在結び:テンション調整の王様。タープやガイラインに必須。
(参考:コールマン公式ロープワーク講座) - もやい結び:固定力が高く、焚き火ハンガーや物干しロープにも使える。
1回結んだらほどけないのに、引けばすぐ解ける万能型。 - 巻き結び:ポールや木にロープを仮留めする定番。
タープを1人で張るとき、これを覚えているだけで設営速度が倍になる。
僕は講習ではこの3つを「10分実践講座」で教える。
「手で覚える」と次の設営から劇的にラクになる。
スマホ片手にコールマン公式ロープ動画を見るとすぐマスターできる。
撤収が早くなる結び方のコツ
撤収のとき、ロープが絡んでイライラする人、多い。
僕がやっているのは、結びを解かずに“外して束ねる”方式。
もやいはループをそのまま残してフック収納、自在結びはテンションを緩めて畳むだけ。
次回設営が2倍早くなる。
“ペグとロープは、テントの骨格じゃない。あなたの安心を支える“信頼の糸”だ。”
次の章では、その信頼を次に繋ぐ「撤収の流れと時短テクニック」を紹介する。
これを知れば、帰り支度のストレスがまるで違う。
4. キャンプ撤収の流れ|時短とストレスを減らす方法
キャンプは設営よりも撤収で性格が出る。
朝の撤収がグダグダだと、せっかくの余韻が台無しになる。
僕も最初の頃は、夜露で濡れたテントをそのまま畳んでカビを生やしたことがある。
それ以来、撤収は「帰り支度」じゃなく、“次のキャンプを始める時間”だと考えるようになった。
撤収は「夜の準備+朝のルーティン」で8割が決まる。
以下は僕がいつもやっている、時短と再利用性を両立した撤収法だ。
撤収前夜の準備|夜のうちに半分終わらせる
ポイントは“朝を楽にする仕込み”。
夜、焚き火を囲みながらでもできることが意外と多い。
- 濡れ物チェック:マットや椅子の裏を確認し、夜露をタオルで拭く
- 小物仕分け:ランタン・調理器具・調味料をケースごとにまとめておく
- 撤収動線をつくる:出入り口付近に収納ボックス・ペグケースを並べる
特に家族キャンプでは、子どもが寝た後の15分整理が翌朝の戦力になる。
これはBE-PAL|キャンプ片付けの時短術でも紹介されている「夜の段取り」法と同じ考え方だ。
朝の撤収ルーティン|乾かしながら片付ける
朝起きたらまずやるのはコーヒー……ではなく、乾燥タイムの確保。
テントやタープを風に当てて乾かしつつ、他の作業を並行する。
この“同時進行”が時短の鍵だ。
- チェア・テーブルを片付け(サイトを広くして動線を確保)
- シュラフ・マットを乾かしながら圧縮袋へ
- タープ・テントの乾燥(フライを外して風通し)
- グランドシートを最後に畳む(地面が乾くまで待つ)
雨の日や夜露がひどい場合は、無理に乾かさず「仮収納」でOK。
コールマン公式「きゃんさぽ」でも、
「濡れたまま畳まず、別袋で収納→帰宅後完全乾燥」が推奨されている。
僕は常に“濡れ物専用コンテナ”を1つ持っている。
乾かす時間がない朝でも、気兼ねなく収納できてストレスがない。
撤収後にやるべき3つのメンテナンス
撤収は現地で終わりじゃない。家に帰ってからの15分が、次のキャンプを決める。
- テントの完全乾燥:風通しの良い場所で2〜3時間陰干し
- ペグ・ハンマーの泥落とし:帰宅直後なら軽く拭くだけでOK
- 収納袋の点検:破損やカビ臭がないか確認。劣化はすぐ交換
この15分をサボると、次の設営で必ず“しっぺ返し”がくる。
逆にここをルーティン化すると、キャンプの回転が速くなり、
準備も気持ちも軽くなる。
撤収時短チェックリスト(風間流)
- ☑ 前夜のうちに小物・寝具をまとめたか?
- ☑ 朝、乾燥タイムを確保したか?
- ☑ 濡れ物を別袋で仮収納したか?
- ☑ 帰宅後の乾燥スペースを確保したか?
これを頭に入れておくだけで、撤収ストレスは半減する。
「撤収が早い人=キャンプを楽しみ尽くせる人」だと僕は思っている。
“撤収の上手さは、経験の証。慌てずに片付ける姿が、一番カッコいい。”
次の章では、そんな撤収のクオリティをさらに高める、
風間流の「設営・撤収の時短ルーティン」を公開する。
5. よくある「設営・撤収の失敗例」とその対策
僕も含め、キャンプを続けていれば誰もが一度は失敗する。
大事なのは“ミスを避けること”じゃなく、ミスを糧にして次をうまくやること。
ここでは僕が300泊の中で経験したリアルな「設営・撤収ミス」と、そこから学んだ“現場で使える対策”を紹介しよう。
❶ テントが傾いた|地形読みとペグ位置の盲点
初めてのソロキャンで僕がやった痛恨ミス。
設営中に「地面が平らだから大丈夫」と思い込んでいたら、夜中に寝袋がズルズル滑る。
原因は、テントを緩い傾斜の下向きに張っていたことだった。
対策:設営前に必ず四隅にペグを仮打ちして水平チェックをする。
もし傾いていたら、その場で位置を数十センチずらすだけでOK。
スノーピーク公式でも「仮張り→全体確認→本固定」が基本プロセスとして紹介されている。
傾きを見抜くコツは、水ボトルを地面に置くこと。転がれば斜面。誰でもできる原始的テクだが、これが一番正確だ。
❷ ペグが抜けた|風下ペグと角度のミス
これは富士山麓で体験した“風との戦い”。
強風の中でタープを張り、ペグを垂直に打ってしまった結果、深夜にバサッ!と音がして布が宙を舞った。
撤収中の隣のキャンパーが「風下ペグ、先に打った?」と一言。……打ってなかった。
対策:ペグは地面に対して60°、風下方向に傾けて打つ。
この基本はコールマン「きゃんさぽ」でも推奨されている。
さらに、ロープは張りすぎず「少し遊びを残す」とテンションが均一に保たれやすい。
僕は以来、必ず最初のペグ4本を“風下から対角線上に”打つと決めている。これだけで安心感が全然違う。
❸ 撤収が終わらない|分担と順番の問題
ファミリーキャンプでよく聞く悩み。「子どもが遊んでて片付けが進まない」「テントが乾かない」。
実はこれ、朝のタスク順と分担ミスが原因。
対策:朝イチに“撤収タスクの順番表”を作っておく。
僕のやり方はこんな感じだ:
- ① 子ども → おもちゃ&寝袋片付け係
- ② パートナー → 調理器具・食器洗い係
- ③ 自分 → テント・タープ乾燥+ペグ抜き係
全員が動線を把握していれば、自然と作業が流れる。
BE-PALの時短撤収特集でも、“役割分担”が最も効率的な撤収法として紹介されている。
❹ ロープが絡まる|収納法のひと工夫
撤収中にロープが絡まり、30分以上格闘したことがある。
そのとき「もう結び直すのが面倒で次回まで放置」。結果、次のキャンプでもまた絡まった(笑)。
対策:撤収時に結び目を解かず、クルクル束ねてまとめる。
もやい結びや自在結びのループは残したままでOK。
コールマン公式ロープワーク講座にも、再利用時短を意識した収納法が紹介されている。
❺ 道具が見つからない|収納場所のルール不足
「あれ?ハンマーどこいった?」は撤収あるある。
僕も何度もハンマーを草むらに忘れ、夜にスマホライトで探し回った。
しかも2回、次の日に戻ってきて拾っている(笑)。
対策:収納ボックスはカテゴリー別に固定位置を決める。
「ペグ・ハンマーは右」「焚き火ギアは左」「調理系は前」と決めておくだけで、探す時間が激減。
帰宅後のチェックもスムーズになる。
風間陸からのメッセージ
キャンプの失敗は、自然が教えてくれる“次へのヒント”だ。
テントが傾いた夜も、ペグが飛んだ夜も、全部いい思い出になる。
その経験を経て、僕らは「ただの宿泊」ではなく自然と対話する時間を手に入れていく。
“キャンプは成功の積み重ねじゃない。失敗を笑って語れるようになった瞬間、キャンパーは本物になる。”
次の章では、その経験をもとに生まれた僕の「設営・撤収の時短ルーティン」を公開する。
手際よく動くコツ、そして“余裕を持つ設営哲学”を伝えよう。
6. 風間陸が教える「設営・撤収の時短ルーティン」
キャンプは“のんびり”が醍醐味だけど、設営と撤収に追われて一日が終わるのはもったいない。
僕はこれまで300泊以上キャンプしてきて、ようやく「30分設営・60分撤収」の型にたどり着いた。
このルーティンを覚えれば、設営も片付けも焦らず・無理せず・ミスなく終えられる。
設営30分ルーティン|“最初の30分”で勝負が決まる
設営のゴールは「風が抜け、動線が整理されたベースを30分で作る」こと。
僕が毎回意識している順序がこれだ。
- 0〜5分:到着→風向と日差しチェック。地形を確認し、出入口の向きを決める。
参考:スノーピーク公式|設営位置の選び方 - 5〜15分:グランドシート→テント本体→ポール→フライ→風下ペグ仮打ち。
強風時はコールマン「きゃんさぽ」推奨の“対角仮固定”で安定化。 - 15〜25分:タープを張り、日陰と作業スペースを確保。
僕は先に焚き火台の位置を決めておく。風の通り道を作るのがコツ。 - 25〜30分:チェア・テーブル・ランタン配置。
設営完了チェックリストで全体を確認してからコーヒーを淹れる。
このルーティンを守ると、風に強く、片付けやすい“合理的なサイト”ができあがる。
僕が講習で初心者に最初に教えるのもこの順番だ。
“設営は作業じゃない。ベースを組むクリエイティブな時間だ。30分の段取りが夜の自由を決める。”
撤収1時間ルーティン|“朝の流れ”をテンポで覚える
撤収はテンションを下げずに、淡々とリズムでこなすのがコツ。
僕が毎回実践している60分プランを公開しよう。
- 0〜10分:朝食&コーヒーを飲みながら乾燥チェック。
風がある日はフライと寝具を外に出して乾かす。 - 10〜30分:チェア・テーブル・調理器具など小物を先に片付け。
“片付けた道具を前方にまとめる”ことで動線を確保。 - 30〜45分:テント・タープ撤収。
濡れ物は仮収納ボックスへ。乾かす時間がなければ別袋で持ち帰り。 - 45〜55分:ペグ抜き・清掃・ゴミ回収。
日本オートキャンプ協会(JAC)が推奨する「Leave No Trace(跡を残さない)」を実践。 - 55〜60分:車積み込み→最終チェック。
忘れ物は“地面の四隅を時計回りに確認”すれば見逃さない。
撤収をルーティン化すると、焦りがなくなる。
僕は撤収中も焚き火を消さず、最後の片付けを“静かな余韻タイム”にしている。
自然に感謝して、また次のキャンプへバトンを渡す感じだ。
“撤収のうまさは、段取りの美学。焦らず、丁寧に、次のフィールドへ。”
風間流 時短ルーティンの考え方
- ⚙️ 動線を先に決める:作業中に道具をまたがないだけで時短になる。
- 🌬️ 風と日差しを味方に:乾燥・調理・快適さすべてが変わる。
- 🧺 “前夜仕込み”を習慣化:撤収の朝は、夜の準備次第で半分終わっている。
- 🕯️ 片付けも演出に:撤収を“締めの儀式”にすれば、余韻が深まる。
このルーティンをベースにすれば、1泊2日キャンプでも「余裕と遊び」が生まれる。
段取りに支配されず、段取りで自由をつくる。それが僕のキャンプ哲学だ。
7. まとめ|設営と撤収が整うと、心まで整う
キャンプでの「設営」と「撤収」は、ただの準備と片付けじゃない。
それは自然と対話するプロセスであり、自分の内側を整える時間でもある。
設営を焦らず丁寧にやれば、夜の焚き火は穏やかに燃える。
撤収を落ち着いて進めれば、帰り道も気持ちよく終われる。
僕はこれまで、風にタープを飛ばされた夜も、雨に濡れて撤収した朝も経験してきた。
でも、どんな失敗も次に活きる。自然は失敗を責めない。
ちゃんと向き合えば、必ず答えを返してくれる。
初心者のうちは、設営や撤収に時間がかかって当然。
焦らず、「一つずつ覚える」ことを楽しもう。
グランドシートを敷く、ペグを打つ、ロープを結ぶ──そのすべてが経験値になる。
気づけばあなたも、“段取りで自由を作るキャンパー”になっているはずだ。
“テントを立てるたびに、少しずつ自分の心が整っていく。
火を囲み、風を感じ、撤収を終えた瞬間に残るのは、心の静けさだけだ。”
もしこの記事が、あなたの「初めてのキャンプ」を少しでも快適にできたなら嬉しい。
次の週末、風向きを感じながらペグを打ってみてほしい。
自然が、きっとあなたの手を導いてくれる。
関連リンク
※本記事は筆者・風間陸の実践経験(延べ300泊以上)に基づき、メーカー公式およびキャンプ協会の推奨手順を参照して構成しています。
安全管理・火気使用は必ず各キャンプ場のルールに従ってください。